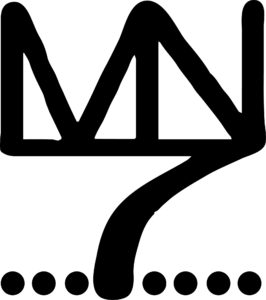【研究の道草】手品と萩原朔太郎
栗原飛宇馬
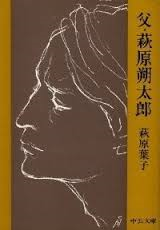
手品と萩原朔太郎(一)
萩原朔太郎が手品に凝っていたことについては、数多くのエピソードがある。中でも印象深いのは、朔太郎が没した直後の話だろう。書斎の机の上に「手をふれるべからず」と書かれた分厚い紙束があり、家人が書きかけの原稿かと開けてみたら全部手品の種明かしだったという。この逸話は、晩年の朔太郎が詩を書けなくなっていたことの証左のようでもあり、どこかもの哀しさがつきまとう。次に掲げる中村真一郎の述懐も、その印象をさらに強めるものである。
私が詩人を見た最後は、恐らく『四季』同人による立原道造の追悼会の席上だったような気がする。
年より早く老いた詩人は、三好達治や丸山薫のような旺盛な活動を行っていた人たちが、活発な議論を戦わせているなかから離れて、部屋の片隅で、ごく若い道造さんの後輩のまだ学生だった私たち数人を前にして、得意の手品を演じてみせてくれたが、それはいかにも孤影悄然という趣きで、二十歳の私たちも、その手品が面白いというより、今や才能の開花の盛りにある後輩たちから撥ね出されてひとりで鬱を晴らそうとしている、一世の大詩人の孤独に冷えきった心にたまりかね、故意に感心した振りをして、歓声と拍手とを送っていたような気がする。(『萩原朔太郎』近代の詩人七、潮出版社)
ここでも朔太郎の手品は、彼の孤独さを際立たせるものとして語られている。私もこれらの話を初めて読んだ時は寂しく思ったし、今でもそう感じる時がある。けれども、当の朔太郎としてはどうだったのだろう。実は存外、そんなことは意に介さず、手品に興じていたのではないだろうか。
そんな想像をしてみたくなるのは、ここ最近、私自身が少々手品に凝り始めたからだ。といっても下手の横好きで、多くを習得しているわけではない。ただ、今はインターネットのおかげで一夜にしてかなりの情報を得ることができる。そうして手品を演じる側の知識を持って朔太郎の逸話を読むと、これまで気づかなかったいろいろなことに目が行くのである。
例えば、萩原葉子『父・萩原朔太郎』(中公文庫)には、赤い玉の手品を無心に練習する朔太郎の姿がたびたび描かれている。家でひとり静かに晩酌する時や、仕事の合間に庭を散歩する時は、たいていこの玉を指に挟んで、四つに増やしたり一つに減らしたりしていたという。「……赤い玉を挟んだその指先は、まるで生きもののように、神経がこまかくかよっているように見えた。この手品は私が子供のころから見ていたが、このころは、ずいぶん上達してきた。」とある。
おそらく、これは「シカゴの四つ玉」と呼ばれる古典的な手品だろう。最近ではあまり見かけなくなったが、ふた昔ほど前までは初心者が覚える定番の手品だった。基本技法が数多く含まれているため、一度は覚えるべき手品とされていたのである。そのため、私などは初級者向けの易しい手品だとばかり思っていたのだが、実はこの手品、マスターするのは至難の技で、それらしくできるようになるだけでも相当な練習が必要なのである。
そう考えると、まがりなりにも玉を増やしたり減らしたりできる朔太郎の腕前は、なかなかのものだったのではないだろうか。朔太郎の手品がずいぶん不味いものであったことは、多くのエピソードが伝えるところだが、右の話などを見ると、それほど下手ではなかったとも思えてくる。無論、これは私の勝手な想像に過ぎないのだけれど、多くの人が途中で投げ出してしまう「四つ玉」を根気よく練習し続ける姿には、同じ手品好きとして共感を覚えるのである。
私自身、難しい技法に挑戦して初めてわかったことだが、手品には〈練習する楽しみ〉というものが確かに存在する。熟練を要する手品ほど上達の喜びは大きく、時間が経つのも忘れて練習に没頭してしまうものなのだ。また、そうした技法は指先が勝手に動くまで体に覚え込ませねばならず、毎日やらなければすぐに腕が落ちてしまう。その意味で、暇さえあれば無心に赤い玉を指に挟んでいる朔太郎は、至極まっとうに手品と向き合っているのである。
おそらく、朔太郎も〈練習する楽しみ〉という手品の醍醐味を存分に味わっていたのではないだろうか。そんな想像をしてみると、手品は朔太郎にとって単なる憂さ晴らし以上のものだったと思えてくる。手品自体が持つ魅力に、朔太郎は多分に惹きつけられていたのである。(つづく)
出典:『日本現代詩研究者国際ネットワーク会報』第30号(2008.4.10発行)p.9-p.10
手品と萩原朔太郎(二)
昭和十五年、第四回透谷賞を受賞した朔太郎は、その祝賀の宴でこんな手品を披露している。
仕舞ひには先生も大分酔はれたらしく、懐中から妙なものを出して、立ち上り
「ハッ??ハッ??ハッ」
と懸け声をなさり乍ら、手品をおはじめになつた。まるで得意満面といふところである。
妙なもの??といふのは、丁度琴の爪のやうな恰好のもので、銀色に光つた金属で出来てゐた。
それを指にはめて、片方の手でその『銀の爪』を掴み抜くと、その『銀の爪』はコツ然と消え失せるのである。私はアツケにとられて、先生の器用な芸当を眺めて居た。(三橋一夫「銀の爪」『文芸世紀』昭和十七年七月号)
ここで「銀の爪」と呼ばれているのはシンブルのことだろう。シンブルとは、もともとは洋裁に用いられる、万年筆のキャップを短くしたような形の指ぬきのことである。いつの頃からか手品に用いられるようになり、今日ではプラスチック製のカラフルなものが手品道具として売られている。原理は単純なのだが、消えたり出したり、瞬時に別の色に変化させたり、と多彩な現象を見せることができる。
朔太郎の演じた手順はごく初歩のものだが、それでも消えたように見せるためには何回も練習しなければならない。私もこの稿を書くにあたって挑戦してみたが、うまく消せるようになるまで三日ほどかかった。朔太郎も夜中に随分稽古をしたという。前掲『父・萩原朔太郎』に、寝床で指先の手品などを研究していたとあるが、その一つはこのシンブルであっただろう。
ところで、この「銀の爪」は朔太郎にしてはめずらしく、手品の成功を伝えている。とかく下手くそぶりが伝えられる朔太郎の手品だが、よく探してみると称賛の声もないわけではない。森房子は同じ号に「あの手品と一緒に、とてもお上手であったギター」と書いているし、『四季』萩原朔太郎追悼号には、多田不二が「マヂツクの天分豊かであつた」と述べている。次に掲げる岩佐東一郎の追悼文とはずいぶん対照的である。
萩原さんは、酔ふと必らずお得意の手品が始まるのだ。その手品が、どうも甚だまづくて、いつも先に種が判つて了ふ。と、萩原さんは、眼を細くして子供のやうにはにかみながら、こんな筈ではなかつたが、と、幾度でも成功するまで繰り返すのだ。始めに種が判つた手品には興味はないからみんな飽きて了ふ。ところが、みんなが無関心になればなるほど、萩原さんの手品はいよいよ白熱化して来るのである。(「故人の印象」『文芸汎論』昭和十七年七月号)
この評価の差はどこから生じるのだろうか。もちろん、演目の難易度の違いや、観客の目の厳しさの度合いにもよるだろう。けれども、手品を演じる者の視点から見ると、これには手品特有の難しさが関わっているように思われるのだ。
手品特有の難しさとは、少しでも失敗すれば終わりということである。朔太郎のように種まで露見しなくても、観客に「今何かやったな」と思われたら不思議さを著しく損ねてしまう。手品が不思議であるためには手品であることすら忘れさせねばならないのだ。
だから、ごく簡単な手品であっても演じ方しだいでとても不思議に見えるし、「名人」と思われることもあるだろう。そもそも種を知らない観客から見れば、その手品が難しいかどうかの判断もつかないのだ。反対に、いくら高度な技法を修得していても、観客の前で少しでもまごつこうものなら「下手くそ」と思われかねない。演じた手品の出来具合によって、朔太郎ほど極端にではないにしても、評価が分かれることは誰にでもあり得るのである。
むろん、だからこそ絶対に失敗しないようになるまで練習することが重要で、朔太郎もそれまでは人前で演じるべきでなかったのかもしれない。だが、ここにもう一つのジレンマがある。熟練するまで見せてはいけないにもかかわらず、手品とは人前で演じなければ上達しないものなのだ。充分に練習したつもりでも、いざ観客を前にすると手が震えたり、予想外の観客の反応に進行が狂ったりする。「こんな筈ではなかつた」という朔太郎の気持ちは、手品を演じる者(特に私のような初心者)には、痛いほどわかるのである。
朔太郎は晩年親交のあった江戸川乱歩に「小生このごろ、マヂシャン倶楽部へ入会して、少しばかり手品を稽古して居ります。近日御邪魔して、下手なところを見ていただきたく存じます」と書き送っている。実際に朔太郎が手品を披露したか定かではないが、手品の嗜みがある乱歩を相手になら安心して演じられただろう。種を知っている愛好家であれば、失敗しても興ざめされる心配はなく、練習として見せるには最適だからである。そう考えると、この書簡もまた朔太郎の稽古熱心さを示しているのではないだろうか。(つづく)
出典:『日本現代詩研究者国際ネットワーク会報』第31号(2008.11.10発行)p.7-p.8
手品と萩原朔太郎(三)
前回まで、朔太郎の手品への熱中ぶりを長々と述べてきた。最後にもう一つだけ、その例を挙げるのをお許し願いたい。マジックの王道ともいわれるトランプにまつわるエピソードである。
前掲『父・萩原朔太郎』によれば、四つ玉やハンカチの出るコップなど、いろいろ見せられた手品のうち、一番印象に残っているのはトランプの手品だという。興味深いのは「外国製の上質のものが買えると、とてもだいじにして、洗面所で、石鹸で一枚ずつ洗っていた」という話である。「これは布でできているので洗えるのだよ」とわざわざ母親にも説明して、たいして汚れてもいないのに楽しそうに洗っていたらしい。この気持ちは、手品をする者でないとわかりにくいかもしれない。
一般には知られていないが、手品には紙製のトランプを用いるのが普通である(プラスチック製の方が丈夫で適しているように思えるが、汗でくっつく等、扱いにくいので敬遠される)。だが、紙製のものは使っているうちにすぐに黒ずみ、くたびれてきてしまうので、マジシャンはトランプのコンディションに常に気を遣わねばならない。巧みな指さばきで密かにカードを操るには、ちょっとでも反っていたり、すべりにくかったりすると都合が悪いのだ。
そのため、プロのマジシャンやマジックの愛好家は頻繁に新しいカードと取り替えている。使い古しのトランプが段ボール一箱あるというのも珍しい話ではない。こうした事情を考えれば、洗えるトランプがいかに便利であるか、朔太郎が得意げに(?)洗っていた理由も十分頷けるのではないだろうか。
けれども、この話には奇妙な点もある。布製のトランプというのは、愛好家にすらその存在を知られていないものなのだ。私も未だ実物を見たことはなく、マジックの歴史に造詣の深いプロの方に聞いてみて、ようやく海外の手芸品でそのようなものがあるとの話を得たくらいである。ただ、それは実用品というよりも土産用の品であり、洗えはするが厚みがあってマジックには不向きとのことだった。
そうなると、朔太郎が持っていた布のトランプとはどのような品だったのか、ちょっとした謎になってくる。が、いずれにせよ、カードの汚れやくたびれを気にするのは、それだけ練習をしていたことの証左といえるだろう。
トランプをめぐっては、他にも、ずいぶん本格的に取り組んでいたことを思わせるエピソードがある。一つは、遺品の中に「トランプのちぐはぐになったみたいなの」があったという話。おそらくこれは通常とは異なる印刷が施されたカードだと思われる。知らない者が見れば確かにちぐはぐで、何に使うか見当もつかないものだが、マジシャンがこれを普通のトランプにまぜて使うととても不思議な現象を起こすことができる。手品がまだハイカラな趣味などと言われていた時代に、よくそんなものまで持っていたと感心してしまう。
もう一つ驚くのは、朔太郎が「フォース」の練習をしていることである。これはカードマジックの高度な技法の一つで、観客にマジシャンの思い通りのカードを選ばせることをいう。観客はあくまで自分の意思で選んだつもりでも、実はそれと気づかずにマジシャンにそのカードを引かされているのである。
「その手つきが、ちょっとうまかったので、初めはタネがわからなかったが、気がつくと一枚だけ特に目につくカードがあるので、別のを引こうとすると、父は、それを引いてくれなくては困る、と言った顔で、私の方へその一枚を苦心して向けてくる。(中略)おかしなもので、私はそれをよけながらも、いつのまにか引いてしまうのだった」と萩原葉子は書いている。これはまさにフォースの練習風景で、娘を相手にくり返し練習していたのだろう。難しいとされる技法にも、熱心に挑戦していたことがわかる。
これほど練習熱心であれば、腕前も少しは上達するはずである。であれば、朔太郎の手品の評判はもう少し良くなってもよさそうなものだが、その下手くそさばかりが喧伝されるのはどうしてだろうか。その原因として、前回は手品特有の難しさを挙げたが、それだけでなく、ここには朔太郎ならではの理由もあるように思われる。次回はこの問題をもう少し掘り下げることで、手品を通して見えてくる朔太郎像に迫りたいと思う。(つづく)
出典:『日本現代詩研究者国際ネットワーク会報』第32号(2009.4.15発行)p.6-p.7
手品と萩原朔太郎(四)
野口武久『朔太郎の日々』(前橋市観光協会)には、当時、朔太郎が所属していた東京アマチュア・マジシャンズ・クラブの幹事だった柳沢義胤の話が紹介されている。
「アマではこれほど物おぼえの悪い人に、今までぶつかったことがない。〈どうもさっぱりわからないから教えてくれ〉というお話で、よく世田谷の萩原さんの自宅に参っては初歩のものの手ほどきをしました。初めハンカチを使う奇術をくり返し伝授しましたところ、これを文士仲間の集まりで演じたそうです。〈ぼくが一生懸命、ハンカチの手品をやって見せて《どうだ、うまいだろう》と胸をはったら、口の悪いのが《なんだ、お前の手品は全部タネがまる見えだ》というから、また練習してやってみせた。〉と萩原さんは語りました。私はこの萩原さんのお話をいつまでも忘れられず、奇術演技の場合の体の角度について、このお話をもち出します。」
指導をする側からみても、朔太郎の下手さは語り草になるものだったようだ。けれども、角度というのは朔太郎に限らず、マジックを演じる者なら誰もが頭を悩ます問題である。正面からは魔法としか思えない不思議な現象も、少し角度を変えただけで種がばれてしまうマジックは少なくない。それなのに朔太郎だけが話題になるのは、何か他に特別な理由があったからではないだろうか。
すぐに思い浮かぶのは、大人になってからもご飯をぽろぽろこぼしまくるという、朔太郎の不器用な食事の仕方である。多くの証言があるように、朔太郎の日常の仕草には不器用さや滑稽さを感じさせるものが多々あった。その印象から言っても、さっそうとマジックを演じる姿より、たどたどしい演技の方が朔太郎には似つかわしく思える。とかくその腕前の不味さが喧伝される背景には、そのような日常の姿が強く影響しているのではないだろうか。
大谷正雄はカフェの女給たちにマジックを披露する朔太郎の姿をこう伝えている。
朔太郎はいつも持ちあるいているトランプで得意? な手品を披露して女達を笑わせ自分も明るく躁いでいた。(中略)朔太郎のその神経質な手つきが、いかにもトランプ手品をするのにふさわしく便利な動作になっていた。別の角度から云うと、何んとも不器用なものなのであった。(中略)朔太郎は顔見知りの全くないカフェーに入ると、さかんにトランプの手品で女達を笑わせ、(多分にお世辞的なものであった)感心している女達には、たわいなく種明しをしてみせ「馬鹿々々しいことなんだよ」と云った。(『萩原朔太郎 晩年の光芒』てんとうふ社)
トランプをいつも持ち歩くところなど、まさにマジック愛好家の習性だが、ここでも手つきの不味さが指摘されている。しかも、たどたどしさゆえに秘密の動作が目立ちにくいというのだから、余程のものだったのだろう。これまで、マジック特有の難しさを述べることで、従来の下手くそという評価にほんの少し異議を唱えてきたが、上手だったというのは難しそうである。
それにしても、なぜ朔太郎はこれほどマジックに惹かれたのだろうか。マジシャンズ・クラブに入会し、本格的に手ほどきを受けたのは晩年のことだが、萩原葉子『朔太郎とおだまきの花』(新潮社)によれば、中学生の頃にはすでに興味をもっていたらしい。最初の結婚生活でも、ヒューズひとつ直せない朔太郎に「下手な手品なんか見せられたって役に立たないけど…」と母がこぼしていたとある。生涯にわたってマジックに関心があったと言えるだろう。
マジシャンズ・クラブに入会してからは、どんな用事をさしおいても、時間も早めに、身なりもきちんとして、毎回楽しそうに出かけていたという。「書きものに熱中している時は寝巻のまま飲みに出たり、時間や日を間違えて会に行くあわてものの父が別人みたいだった」と萩原葉子は書いている(前掲『父・萩原朔太郎』)。マジックに対する姿勢からは、萩原朔太郎の様々な面が見えてきそうである。(つづく)
出典:『日本現代詩研究者国際ネットワーク会報』第33号(2009.10.1発行)p.5-p.6
手品と萩原朔太郎(五)
全集未収録の朔太郎書簡を集めた「前橋文学館研究紀要」第二号に、「四季」編集部宛の返信葉書が掲載されている。会合の都合を聞かれたものらしく「木曜日は、午前中、学校の講義があり、夜は手品の会がありますので、他の日に変更していたゞき度特にお願ひ致します」とある。詩よりもマジックが大事だったわけではないだろうが、マジシアンズ・クラブの例会は外せない用事だったようだ。
前回、朔太郎が文士仲間の集まりで手品を披露したところ「全部タネがまる見えだ」と言われた話を挙げたが、これには続きがある。再度練習して演じても「まだ見える」と言われてしまう。「それからまた一所懸命練習して、3度目の正直とやってみせた。『こんどは見えないだろう』と言ったら、『ああ、こんどは見えない。全然みえない。君の体のかげになって、何をやっているのか全然みえない』と言うではないですか。ぼくには奇術はダメでしょうかね」そう朔太郎はクラブの例会で語ったという(『TAMC50年のあゆみ』)。冗談めかして失敗談を語りながら、同好の士の集まりを楽しんでいる姿が目に浮かぶ。
それにしても、なぜ朔太郎はこんなにもマジックに夢中になったのだろうか。そこにはやはり〈孤独〉ということがあるのかもしれない。
吉行淳之介の「手品師」という短編小説に、朔太郎とおぼしき人物の挿話がある。
「倉田はそのささやかな手品を眺めながら、一人の詩人についての挿話を思い浮べていた。その秀れた詩人は、厄介な人間関係に巻き込まれたあげく、妻に去られ、孤独な晩年を送った。幼い娘が一人いた。ある夜、娘が二階の書斎を覗いてみると、机の前に坐った詩人がしきりに指を動かして、赤い指の玉の練習をしていた、という。/倉田はその挿話を聞いたとき、詩人の孤独感が身に沁み込み伝わってくるのを覚えた。」
マジックには〈練習する楽しみ〉があると前に書いたが、それは確かに孤独を紛らすのにうってつけの方法でもある。無心で手を動かすことに没頭できるので、寂しさも何もかも忘れさせてくれるのだ。右の小説に登場するマジックの得意な青年も、人とのコミュニケーションが苦手な、子供じみた孤独な若者として描かれている。
また、マジックにはそのような劣等感を持つ者が、相手をひっかけて束の間の優越感に浸るという、あまりいい趣味とはいえない側面がある。演じる者にその快楽が全くないといえば嘘になるだろう。本当に楽しいマジックを演じるのは、実は指先の技巧よりも難しいものなのだ。
だが、朔太郎がマジックにのめり込んだ理由はそれだけなのだろうか。いや、優越感を得るのが目的なら、手ひどい失敗を繰り返した時点でマジックから遠ざかるはずである。朔太郎がこんなにもマジックを続けたのは、その最初の動機として、マジックへの感動があったからだろう。
そう感じさせるエピソードが『父・萩原朔太郎』にある。選んだカードを当てる朔太郎に、娘がどうして分かるのか聞く。すると朔太郎は「『これか? これは、つまりサイコロジーの応用だよ』と、得意そうに言うのだった。サイコロジーとは、心理学のことだそうである。父は、このサイコロジーということをよく言った。特に手品の時は、かならず、サイコロジーだよと何度も言った。」
これは実は、本当の種を明かさないためにサイコロジーと言っているにすぎない。マジックの原理で、厳密に心理学に根差したものはそうないはずである。
私は、タネ明かしが、いちいち知りたくなって、父のすぐ前で見ていると、タネのカードを落としたり、ぎごちない手つきをするのである。「あ! わかった」と、私が喜んで言うと、酔眼を大きく開け、あわてて細い指先でトランプを持ち直し、「葉すけは、目を光らせて、タネ明かしばかり知りたがって、だめだなあ、もっと離れて見ていなければいけないよ」と、言う。/私が「タネ明かしを教えて」と言うと、ごく初歩のだけ、少し教えてくれたが、あとは「マジシャン・クラブの規定で教えられない」と、決して教えてくれないのだった。
種が分からないように苦心するのはマジシャンの常だが、朔太郎は手品道具を入れた引出しに鍵を掛け、種を記した紙に「手をふれるべからず」と書くなど、律義さが非常に目立つ。だがそれは、逆説めくが、マジックの本当の面白さが種にはないことを、朔太郎が知っているからだと私には思われる。
極上のマジックを目の当たりにすると、種明かしなどどうでもよく思えることがある。その感動を知っているからこそ、種の扱いにデリケートになるのだ。「タネ明かしばかり知りたがって、だめだなあ」と朔太郎が言うとき、そこには、観る者に味わってほしい〈不思議〉への想いが込められているように思えてならない。かつて自身が経験した〈不思議〉への感動が、マジックをする動機の根源にあると考えられるのだ。
だがそれは同時に、秘密をいつも胸にしまっておくことを要求する。マジックを演じる者もまた、時に秘密を明かしたい誘惑にかられるから、それはなかなか自制心を要するものである。それはどこか、時に〈ダンディズム〉と評される朔太郎の姿勢に通じるものがあるのではないだろうか。(了)
出典:『日本現代詩研究者国際ネットワーク会報』第34号(2010.7.10発行)p.9-p.11
執筆者略歴:くりはら ひうま
文学研究者。博士(芸術学)。学位論文「萩原朔太郎研究・思索の軌跡」(『江古田文学』59号)、連載「詩人と戦争 晩年の萩原朔太郎をめぐって」(『江古田文学』73号~80号)ほか。
マジックと朔太郎に関しては「手品と文学―乱歩と朔太郎の共鳴源」(展示図録『パノラマ・ジオラマ・グロテスク 江戸川乱歩と萩原朔太郎』)、「萩原朔太郎の愛した〈不思議〉―手品・乱歩・『詩の原理』」(萩原朔太郎研究会会報『SAKU』第82号)等がある。
magic repository